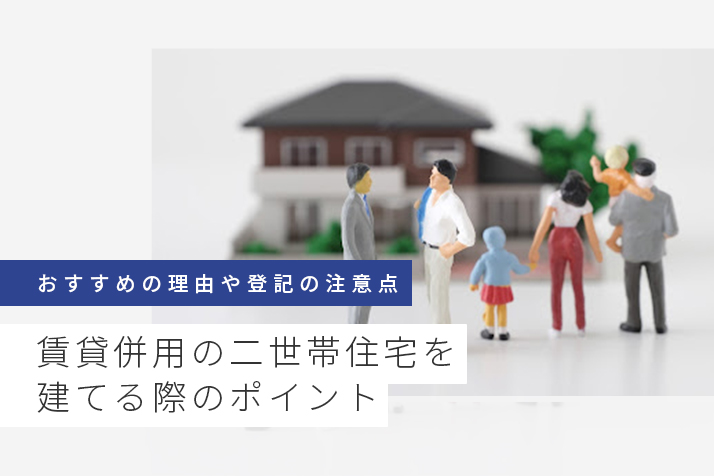
渡辺知哉
設計事務所・大手ハウスメーカー・不動産ベンチャーを渡り歩き、ランディックスにジョイン。 設計事務所時代は戸建住宅をメインに設計しつつ、その他はビル・マンション・オフィス・ショップ等広く設計業務を担当。 ハウスメーカーでは営業・設計・IC業務を兼務。ベンチャーではリノベーションのワンストップサービス業務を担当。営業・設計の両面からサポートします。
この記事の監修者
渡辺知哉
設計事務所・大手ハウスメーカー・不動産ベンチャーを渡り歩き、ランディックスにジョイン。 設計事務所時代は戸建住宅をメインに設計しつつ、その他はビル・マンション・オフィス・ショップ等広く設計業務を担当。 ハウスメーカーでは営業・設計・IC業務を兼務。ベンチャーではリノベーションのワンストップサービス業務を担当。営業・設計の両面からサポートします。
賃貸併用住宅の賃貸経営を始める際は、建てる目的や入居者層の絞り込み、資金計画の立案をしておく必要があります。なぜなら、経営を始めると想定外のリスクが発生する恐れがあるからです。この記事では、賃貸併用住宅で10年後に起こり得るリスクや事前準備のほか、10年後に失敗しないためのコツを解説します。
賃貸併用住宅の新築当初は、満室でローンの支払いも順調で余裕があることもあるでしょう。しかし、10年を超えると様々なリスクが起こりやすくなります。
ここでは、賃貸併用住宅で10年後に起こり得るリスクとして以下の5点を解説します。
空室が続くと家賃収入が減るため、そこから月々の経費を差し引くと手元に残る収入が減少するリスクがあります。
10年を超える場合の空室リスクは、以下のような原因が考えられます。
|
空室は、建物の築年数や立地条件の影響を受けて発生する傾向にあります。賃貸経営を悪化させる最大の要因となるといえるでしょう。新築当初に好スタートで発進したとしても、空室リスクが常にあることを念頭に入れておく必要があります。
築年数が経つにつれて、様々な箇所の老朽化が進みます。築10年であれば、外壁の塗り直しや屋根の雨漏りという大きな修繕はあまり発生しません。どちらかといえば、
長期使用による寿命や突発的な損傷が挙げられるでしょう。そのままにしておくと入居者も敬遠しがちです。
また、耐久性の低い建物は外壁にヒビが入るようなケースも見られます。見た目の印象は、入居率を左右する重要な要素です。そのため、家賃を下げないと入居者が集まらなくなるという事態を引き起こします。
賃貸経営をしていく上では、地震や火事など予期しない災害の発生により家賃収入がなくなるというリスクがあります。このところの台風被害も気になる方も多いでしょう。
被災するとその被害額が大きく、建物の被害についてはオーナーが修繕費用を負担しなくてはなりません。建物の損壊により入居者がケガを負った場合は、損害賠償も発生することも考えられます。災害により家賃収入がなくなり、さらに修繕費がかさむようだと、ローン返済が滞ることにもつながります。
入居者トラブルにより当事者だけでなく、他の入居者も退去するというリスクがあります。トラブルの代表例は、音の問題です。できるだけ円満に解決したくても、なかなか解決に至らない問題でもあります。
対応が難しい理由として、以下の内容が挙げられます。
|
音に関しては、住み心地に影響する重要な問題です。様々な生活音が発生するため、オーナーが現状を正しく把握して適切に対応するのは難しいといえます。
家賃滞納が続くと家賃収入が減るだけでなく、その期間は新規の入居者募集もできないというリスクを負うことになります。賃貸併用住宅は、入居者との距離が近いことから、家賃の支払いを促しにくいという声も聞かれます。少しなら待っても良いと曖昧にすると、かえって滞納が解消しないケースも少なくありません。空室リスクとならんで起こりやすい問題です。

賃貸併用住宅で賃貸経営を始めるにあたり、10年後を見据えた事前準備が大事です。しかし、どこに重点を置いて、事前準備を始めたら良いのか分からないという方も多いでしょう。
ここでは、賃貸併用住宅の賃貸経営を始める事前準備として、以下の観点で解説します。
賃貸併用住宅をどのような目的で建てるのか、その目的を明確にする必要があります。なぜなら、賃貸併用住宅を建てる目的によって賃貸の規模やローンの借入額が変わってくるからです。
賃貸併用住宅を建てる目的としては、主に以下のようなものが挙げられます。
いずれの目的に共通しているのは、収益がプラスになることが前提になるという点です。目的を明確にすることは、賃貸併用住宅における賃貸経営で失敗しないための第一歩になります。
賃貸併用住宅を建てる場合、入居者層を絞り込むことが大切です。ターゲットとなる入居者に合わせた間取りや設備のほか重視するポイントが異なるためです。さらに、もっと先を見据えた10年後も収益を生むための空室対策にもつながります。
入居者層を絞り込むには、施工会社任せにせず、建築予定地に直接出向いて確認するのが良いです。
以下に示す項目をチェックしましょう。
得られたデータを元に、どの入居者層を選ぶと集まりやすいのかを考え、間取りや設備を決定します。
賃貸併用住宅を建てる理由や入居者層の絞り込みに続いて、資金計画を立てていきます。
資金計画では、賃貸併用住宅を建てるのに必要な費用を見積もっていきます。主な費用は、以下の通りです。
賃貸併用住宅の建築には、建物本体の工事費用に加え付帯工事、税金、諸費用がかかります。おおよその内容は、以下の通りです。
| <本体工事費用>
基礎工事 木工事 屋根工事 建具工事 防水工事 外壁工事 内外装工事など | |
| <付帯工事費用>
解体工事(建て替えの場合) 地盤工事(軟弱な地盤の場合) 電設工事 給水工事 ガス工事 家具工事 外構工事 植栽工事など | |
| <税金・諸費用>
不動産取得税:賃貸併用住宅を取得した時に課される税金 登録免許税:所有権保存登記など登記にかかる税金 印紙税:売買契約書など契約書に課される税金 ローン関連の手数料 火災保険料など |
賃貸併用住宅の賃貸経営は、必要経費が発生します。主な経費は、以下の通りです。
| 概要 | |
| 租税公課 | 事業に関わる税金や公的負担金のこと
例)固定資産税、不動産取得税、商工会などの会費 |
| 損害保険料 | 事業用資産に対する損害保険料
例)火災保険、地震保険 |
| 減価償却費 | 固定資産の取得費用を耐用年数に合わせて分割計上する費用
例)建物、設備、備品 |
| 修繕費 | 建物や器具備品などの改修・修繕費
例)建物の修理費、設備機器の点検費用、外壁の塗り替え |
賃貸併用住宅の賃貸経営にかかる税金は、下表の通りです。
| 概要 | |
| 所得税 | 家賃収入(不動産所得)から必要経費を差し引いた金額に応じて課される税金のこと
給与所得などの所得と合算して課税される ※給与以外の不動産所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要 |
| 固定資産税
都市計画税 | 賃貸併用住宅の土地・建物にかかる税金のこと
都市計画税は、賃貸併用住宅が市街化区域内に建てられた場合のみ 土地・建物に課せられる税金のこと |
賃貸併用住宅の資金計画は、10年後を見据えた賃貸経営を安定させるために非常に重要です。そのためにも、様々なリスクを考慮して作成しなければなりません。高い専門知識を必要とするので、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、無理のない計画になるよう検討しましょう。
賃貸併用住宅の賃貸経営を行う準備として、自己資金を十分に確保することも重要になります。手元に十分な資金があると、リスクへの対応力が高まるからです。
建築費用(本体工事費用と付帯工事費、税金・諸費用の総額)から自己資金を差し引き、不足分をローンで融資を受けます。自己資金が不足すれば、ローン返済の負担が大きくなるのは言うまでもないことです。リスクに対応するのも難しくなってしまうでしょう。
自己資金が多ければ借入金額が減り、月々の返済額を抑えることが可能です。さらに、急な出費にも対応できるでしょう。自己資金を十分に確保できると、リスクに対する資力が高まるといえます。

賃貸併用住宅の賃貸経営における様々なリスクや事前準備について把握したところで、ここでは賃貸経営で失敗しないためのコツを解説します。
賃貸併用住宅の購入10年後に失敗しないためのコツは、以下の6つが挙げられます。
空室・家賃滞納・クレーム対応といったリスクをできるだけ回避して、長期的に安定した賃貸経営をするためには、信頼できる管理会社への委託がおすすめです。
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会が、管理会社が管理している賃貸物件について、半期ごとに「賃貸住宅市場景況感調査」を発表しています。
調査結果によると、
|
昨今は、空き家率13.6%(平成30年住宅・土地統計調査)で過去最高といわれる状況において、管理会社に委託すると空室率を低く抑えられるといえます。賃貸経営の実績がある管理会社であれば、クレーム対応や入居者募集などのノウハウも持っていることが多いので安心です。賃貸併用住宅の賃貸管理について不安がある方は、管理会社に委託することを検討してみましょう。
参照元:第26回『賃貸住宅市場景況感調査日管協短観』2021年4月~2022年3月|公益財団法人日本賃貸住宅管理協会日管協総合研究所
賃貸併用住宅における建物の老朽化に関するリスクは、入居者が退去した時の原状回復や日常的に起こる修繕のほか、災害時の修繕、最も高額な費用を必要とする外壁塗装や屋根の修繕まで、長期にわたり起こり得ることを紹介しました。
修繕費用は、新築当初から先を見越して積み立てておくことが大切です。その都度、手出しで行うと負担が大きく、費用の調達ができない場合には修繕ができなくなってしまいます。
ある程度計画的に修繕を施すことで、建物の老朽化スピードを遅くできます。修繕費用の積み立ては、老朽化リスクに対する唯一の対策といえるでしょう。
自然災害によるリスクは、どれだけ注意を払っていても防止できるものではありません。そのような対策には火災保険の加入が必須です。
▶火災保険
火災をはじめ落雷、台風、雪災により、賃貸併用住宅の建物および家財に損害が生じた際に保険金が支払われます。ただし、地震による火災には補償されないので、地震保険への加入も検討してみてください。
また、賃貸経営向け火災保険には、家賃補償特約があります。火災による建物の消失や大雨による床上浸水などのケースで、家賃収入が得られなくなった場合の損失額を補償する特約です。補償内容は各保険会社で異なるので、問い合わせて確認しましょう。
▶地震保険
地震リスクの対策としては、地震保険が一般的です。震災による被害の対策として加入する人が増えています。火災保険と合わせて契約する必要があり、地震保険単独で加入できません。火災保険は確定申告で控除を受けることはできませんが、地震保険は地震保険料控除の対象となるので、賃貸併用住宅では検討の余地があるでしょう。
賃貸併用住宅の賃貸経営を始める前に、具体的な資金計画を立てておきましょう。長期の資金計画を立てることになるため、どの程度の支出があるか分析しなければなりません。必要な支出として、ローン返済額や修繕費、火災保険料、管理会社に管理を委託するのであれば管理費、固定資産税など具体的に洗い出していくことが大切です。
収入面では、家賃収入の計算を満室のケースだけでなく、一定の空室率をしっかり見込んでおくことも忘れずに行いましょう。具体的な資金計画には、理想的な数値ではなく、より実際的な数値を用いて分析することが重要なポイントになります。
賃貸併用住宅の賃貸経営では、家賃収入の変動やローン金利の上昇などがあるため、資金計画を立てても想定通りになるとは限りません。そのため、定期的に見直す必要があるのです。
資金計画の見直しは、現状の経営状態に基づいて以下のポイントを押さえましょう。
資金計画は、現状の収入と支出を明確にした上で、家賃の値下げや空室、滞納、退去といったリスクを加味する必要があります。できるだけ多くのリスクを考慮して、定期的に見直していきましょう。
賃貸併用住宅の購入に失敗しないために、賃貸併用住宅の建築会社を厳選することも有効です。建物の老朽化によるリスクは、修繕費を積み立てて早めのメンテナンスが欠かせませんが、施工品質の高い建物を建ててくれる建築会社を選ぶことも重要なポイントになります。
低品質な建物は老朽化も早く、修繕費用も資金計画で想定した額に比べ高額になりがちです。建築費を抑えることを重視すると、かえってリスクを負うことになります。同じように考えると、設備のグレードにも相応のコストをかけると、入居者ニーズを満足させ、空室リスクや家賃値下げのリスクを小さくできるでしょう。
賃貸併用住宅の建築会社を厳選するには、賃貸併用住宅の施工実績が豊富で、技術的にも信頼がおける建築会社を選びましょう。
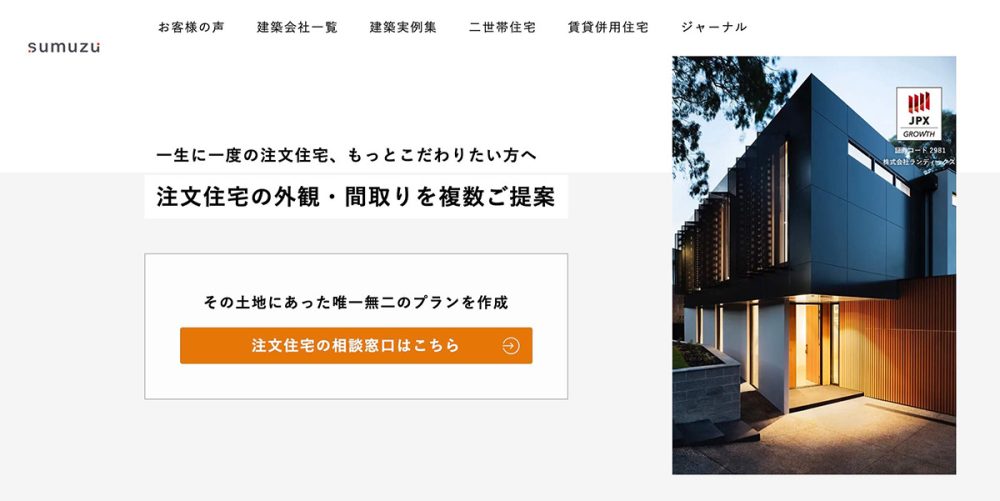
賃貸併用住宅の賃貸経営はメリットも多いですが、多様なリスクもあります。初めて建築する方であれば、分からない点が多くあるのも当然です。リスクに関して、理解しやすく説明してくれる建築会社を選びたいという方も多いでしょう。
そういった方におすすめしたいのが、株式会社ランディックスが運営する、注文住宅マッチングサービス「sumuzu(スムーズ)」です。
sumuzuはお客様の家づくりを中立的な立場からサポートする専門家集団です。工務店・ビルダー・ハウスメーカー・設計事務所の選び方から、お客様のご希望に合わせた間取り計画・工事見積りの減額調整まで、家づくりに関する全ての悩みについてご相談いただけます。
なお、建築会社は、厳格な審査を通過した信頼できるハウスメーカーや工務店、建築家などが参加しています(建築会社一覧)。
資金計画を立てる上で重要になる、住宅の希望条件、予算に加えて、住宅ローンの紹介といった資金面の相談が可能です。見逃しがちな火災保険やアフターサービス、引っ越しについても相談可能です。さらに、インテリア、エクステリア、セキュリティなどにも対応しておりますので、住宅に関する様々な面をカバーしているということになります。
なお、これらの相談、ヒアリングなどは、チャット、メール、電話などで対応可能です。具体的な話は面談が必要ですが、オンラインによる面談(Zoom)にも対応しています。忙しい方にも安心の対応です。
この記事では、賃貸併用住宅で10年後に起こり得るリスクや事前準備のほか、10年後に失敗しないためのコツを解説しました。想定されるいくつかのリスクをゼロにすることは難しいですが、できるだけリスクを抑えることはできます。そのためには、10年後までを視野に入れて資金計画を行い、現状に基づいて定期的に見直すことが大切です。また、多くのリスクは、品質の高い建物を建てることでも回避できるといっても過言ではありません。
賃貸併用住宅を検討する上で、少しでも不安があれば、家づくりの専門家への相談もおすすめです。賃貸併用住宅の実現に向けて、sumuzuの利用を検討してみてはいかがでしょうか。